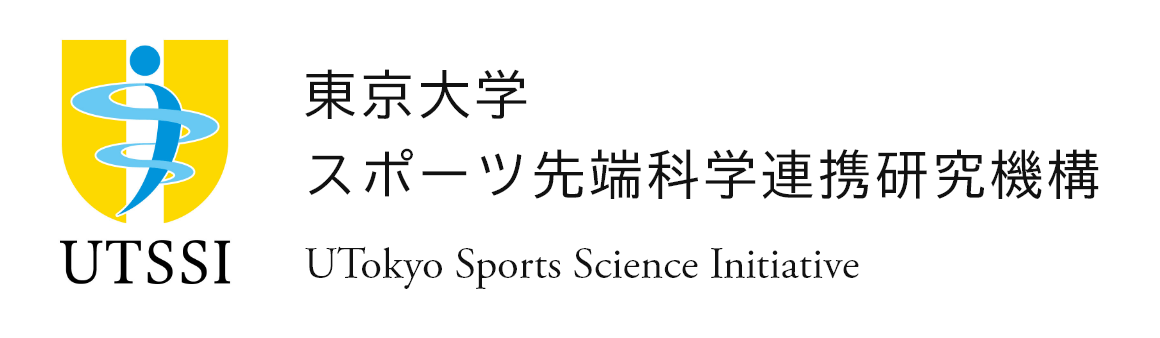何歳になっても、昨日できなかったことが今日できるようになる。そんな肉体の限界突破を支援したい。
01 稲見 昌彦(先端科学技術研究センター 副所長・教授)

先端的かつ多角的なアプローチで新時代のスポーツ・健康科学を推進する東京大学先端スポーツ科学研究連携機構(UTSSI)には、そのミッションに賛同した約50名の研究者たちがUTSSIのメンバーに名を連ねています。このコーナーでは、その多様な顔ぶれの一人一人にフォーカスを当て、研究の原点や、今後の展望、UTSSIの活動についてなどをインタビュー。今回は、機器や情報システムを駆使して人間の持つ運動機能を拡張し、工学的にスーパーマン(超人)を生み出そうとする「人間拡張工学」を専門とする東京大学先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授にお話をうかがいました。
-「身体の自在化」を切り口に、テクノロジーの力で人間の身体の拡張を目指す「人間拡張工学」を研究テーマとする稲見教授。研究の道へと進む原点にあったものとは?
私は小学生の頃、非常に運動音痴でした。そんな私が共感とともに夢中になったのが『ドラえもん』です。私にもドラえもんがいて秘密道具があれば……と思いつつ、当然、ドラえもんは来てくれない。ならば、自分で秘密道具を作れるようになりたい! というのが研究者としての出発点でした。今でも行き詰まったときは『ドラえもん』を読み返し気づきを得ることがあります。

秘密道具以外でも『ドラえもん』からのヒントは多いです。劇場版「のび太の宇宙開拓史」の舞台であるコーヤコーヤ星は地球より重力がずっと小さいため、のび太自身は何も変わっていないのにスーパーヒーローになれる。これはすごいことだぞ、と感じました。環境が変われば、人ができることの選択肢や可能性が変わる。その「環境」を作ることが今の私の研究と言えます。
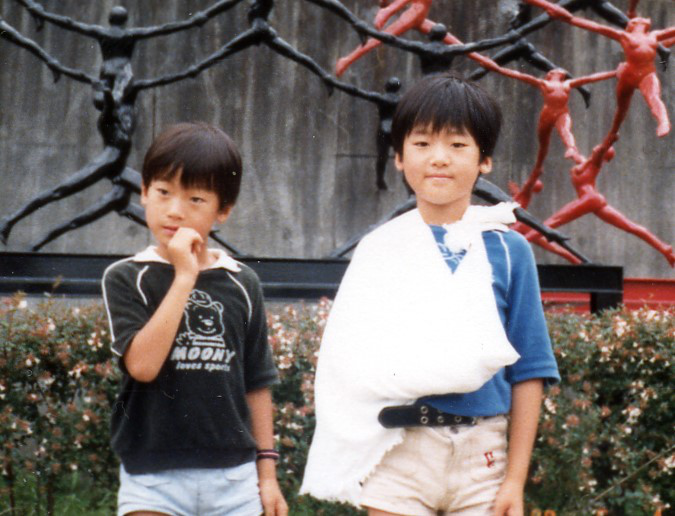
たとえば、私の研究室の博士課程学生の川崎仁史さんが開発した「けん玉できた!VR」は、重力を小さくしてスローモーションの世界を作るコーヤコーヤ星的な発想です。スローモーションでけん玉のトレーニングをすると、ボールが落ちてくる瞬間、ふわっと受け止めることができるので基本的な動作がよくわかります。
私のような運動音痴にとって、この現実世界はゲームに喩えるとハードモードです。ハードモードでは失敗しやすく、しかも何度も失敗するために諦めがちになります。そこで、VR(バーチャルリアリティー)によってイージーモードの世界を作り、適切な成功と失敗を繰り返すことで現実世界でも早く習得ができるようになる。この「けん玉できた!VR」を5分ほど試したことで実際にけん玉が上達した人は大勢いますよ。
<けん玉できた!VR>
--「けん玉できた!VR」以外でも、SF映画「攻殻機動隊」に出てくる技術「光学迷彩」の実現や、メガネ型ウエアラブルデバイス「JINS MEME」の共同開発など、稲見教授の研究成果は多岐に渡る。のび太がスーパーヒーローに…の観点でいえば、人間と機械が融合した「超人スポーツ」の提唱もそのひとつだ。

スポーツでは「する」「見る」「支える」の3つの軸が重要とよく言われます。でも、今あるスポーツも、かつて誰かが作ったもの。時にはスポーツを「作る」視点もあってもいいのではないか、という発想です。22世紀で人気のスポーツが実は21世紀初頭の日本で生まれた、なんてことがあれば素敵なことですよね。
現在、人気のスポーツの多くは、産業革命によって肉体労働から解放された人々がエンターテインメントとして始めたものです。その産業革命の発展の先で新たなテクノロジーを使ったモータースポーツが生まれ、次は情報革命によってeスポーツも生まれて、今まさに広まりつつあります。
では、この先は何か。人を支援して拡張するような技術を使うことで、今のオリンピック・パラリンピックという枠組みそのものも変えるようなスポーツができるかもしれない。その一例がAR(拡張現実)の技術を活用した超人スポーツのひとつ「HADO」で、今では競技人口が世界で約600万人、ワールドカップも開かれています。
といっても、私は「超人スポーツ」というコンセプトを考えただけ。そのコンセプトをもとに、エンジニア、ゲームクリエイター、アーティストなどさまざまな領域の人が「自分も何か手伝わせて」と集まり、勝手に広がっていきました。
改めて思うのは、研究者の初期のキャリアでは「自分だったらこうするのに」「これは良くないからこうしてみよう」と森羅万象にツッコミを入れていく「ツッコミ力」が必要ですが、それを社会に広め、コミュニティを形成する上では「ボケ力」が重要です。適切なツッコミを誘うようないいボケをすると、「自分ならこうするよ」といった良いサポートが生まれ、コミュニティが広がっていくのだと思います。
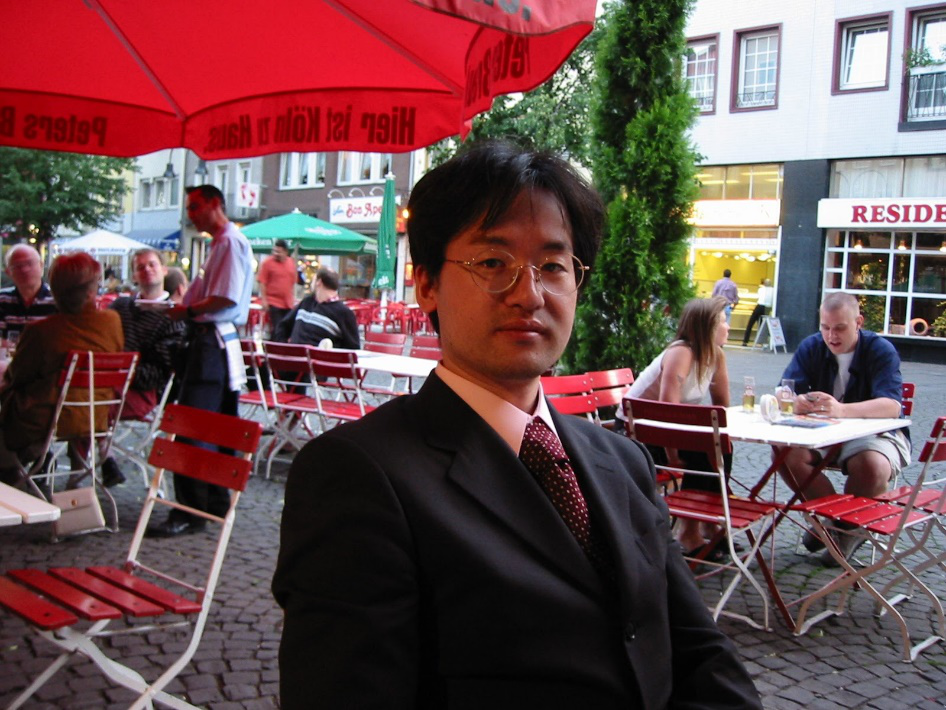
-すでに今の社会でも大きな成果を生み出している稲見教授の「人間拡張工学」。この先30年、40年を経た未来では、さらにどう発展していくイメージなのか?
もう数年もしないうちに、今の社会活動におけるほとんどの領域でAIやロボットが人間を凌駕します。そこで人間にとって必要になるのは「推しの世界」です。
私の研究室のアドバイザーをお願いしている山本一成さんは、将棋ソフトPonanzaの開発者で、はじめてプロ棋士にPonanzaが勝利したときは大きなニュースになりました。その後もAIはさらに進化し、名人にも勝てるようになった。ところが、そのことはもう世間ではあまり話題にはならず、みんな藤井聡太七冠の話しかしない。ここにヒントがあると思っています。
野球でも、人間が投げられない豪速球を投げるロボットの開発、その豪速球を打つロボットを作ることはできますが、みんなが応援するのは大谷翔平選手のはず。人間を完全に超えて強くなりすぎると、もうそれは競争の対象でも応援する対象でもなく、便利な道具になってしまう。
そして人間は、便利な道具よりも、自分から少しだけ離れている能力を持つ人を推したくなるもの。その推したくなる立場の人を支援すること、もしくは、推し活そのものを支援するシステムを作ることもUTSSIのこれからの目標となるのかもしれません。
-未来を見据える稲見教授が伝えたい、共同研究をする企業、そしてこれから研究の道に進む学生へのメッセージとは?
世の企業に向けては、大学にすでにある技術を使おうとするのではなく、「何をやるか」から一緒に考えましょう、ですね。それが一番産学連携がうまくいく方法だと思います。その企業が持っている問題意識と、変な物を作る能力のある我々の知見が掛け合わさると、結果的にハイブリッドな物が生まれ、社会実装まで至ることが多いです。

今の学生は皆さんモチベーションも意識も高く、自発的に研究を始める学生ばかり。もう伸びしろしかないので、今の方向のまま頑張って欲しい。その研究のもとに東大スポーツも強くなって欲しいですね。
私がUTSSIに貢献できることは、トップアスリートを作ることだけではなく、トップアスリートを作るテクノロジーや新しいトレーニング法の推進に尽力すること。この点では世界に貢献できるはずです。もし興味がある学生がいたらどんどんやってほしい。その後押しをする場として、UTSSIにある人・資金・知見をぜひ活用してください。
プロフィール

稲見昌彦(いなみ・まさひこ)東京大学先端科学技術研究センター副所長・教授。超人スポーツ協会発起人。米マサチューセッツ工科大学コンピューター科学・人工知能研究所客員科学者、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授などを経て、2016年4月より現職。2018年より東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター応用展開部門長を兼務
取材・文/オグマナオト
撮影/布川航太
関連リンク UTSSIについて(企業・各種団体のみなさまへ)