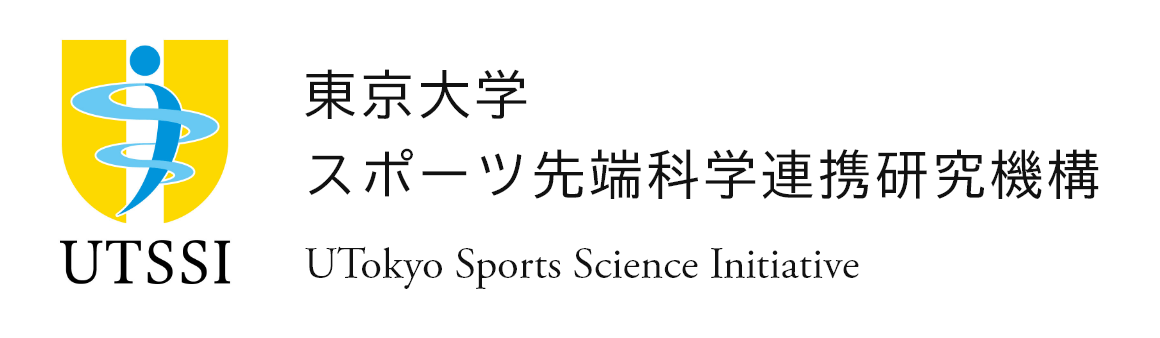スポーツをきっかけに、人とつながり、地域に自分の居場所ができていく。そんな循環を、“まちづくり”の力で生み出したい。
03 小泉 秀樹(東京大学先端科学技術研究センター・大学院工学系研究科 教授)

先端的かつ多角的なアプローチで新時代のスポーツ・健康科学を推進する東京大学スポーツ先端科学連携研究機構(UTSSI)には、そのミッションに共鳴した約50名の研究者たちがUTSSIのメンバーに名を連ねています。このコーナーでは、その多様な顔ぶれの一人一人にフォーカスを当て、研究の原点や、今後の展望、そしてUTSSIとの関わりについてなどをインタビュー形式で紹介していきます。
今回は、都市計画や地域デザインを専門に、人が主役となる「まち」の姿を考え続けてきた東京大学大学院工学系研究科の小泉秀樹教授が登場。UTSSIの一員として、「スポーツまちづくり」というテーマに取り組み、スポーツが地域や人をどう繋げていくのか、新たなまちの可能性を探っています。
── 先端科学技術研究センターで「共創まちづくり」をテーマに掲げる小泉秀樹教授。学生時代に「都市計画」の世界に足を踏み入れ、いつしかその関心は「スポーツ」にまで広がりを見せている。そもそも「都市計画」と「まちづくり」は何が違うのか?
日本と欧米では、都市計画の背景から異なります。都市生活全般を見据えてより広域な視点からプランニングされる欧米に対し、日本では国交省や経産省、環境省など、複数の省庁が都市計画に関わるため、縦割り構造のなかで十分な連携が取れず、非常に狭いエリアでしか都市計画が成立していません。
一方、地域の生活像や空間像など、コミュニティも内包してトータルに考えるのが「まちづくり」という視点です。住民参加、住民主導で考えることも重要なポイントで、現代においては少子高齢化、人口減・世帯減なども踏まえながら、地域の未来を描く。この「まちづくり」に「スポーツ」を掛け合わせる発想が、私の提唱する「スポーツまちづくり」です。
──その「スポーツまちづくり」の象徴的事例とも言えるのが、2024年に誕生した2つのJリーグスタジアム、サンフレッチェ広島の「エディオンピースウイング広島」と、V・ファーレン長崎の「長崎スタジアムシティ」だ。共にサッカースタジアムをハブとする新たなまちづくりとして大きな注目を集めた。
両スタジアムとも、地元ターミナル駅であるJR広島駅・長崎駅からそれぞれ徒歩圏内という好立地であることから、「街なかスタジアム」とも称されている。この2つの事例について、小泉教授はクラブやJリーグと協力して社会的意義を可視化する研究を進めている。

かつて、日本のスタジアムは郊外の空き地に建てられることが一般的で、「まちづくり」としての発想が十分に取り入れられていませんでした。一方で、広島や長崎のように「街なか」にスタジアムを整備した場合、どのような影響が生まれるのか──その変化はデータでも明らかになりつつあります。
たとえば、環境面では炭素排出量に大きな違いがあります。郊外型スタジアムでは車移動が主になりますが、都市中心部であれば鉄道やバス、徒歩によるアクセスが可能となり、結果としてCO₂排出量を抑えることができる。さらに、中心部の商店街に立ち寄る人が増加していることも調査から判明しています。私たちはサンフレッチェ広島と連携し、定期的に来場者へのアンケートを実施。試合後の動線や消費行動などについてデータを蓄積してきました。
これらの取り組みは、UTSSIの下にある「スポーツの価値学(明治安田生命)寄付研究部門」においても、学内外の研究者と知見を共有しながら、双方向的な研究へと発展させているところです。


── そもそも、「まちづくり」を専門としていた小泉教授が「スポーツまちづくり」へと領域を発展させるきっかけとなったのもサッカーだった。
私自身、サッカーが好きで、とくにドイツではフットボールクラブが地域コミュニティを形成する上で重要な役割を果たしていることから、このテーマに関心を持つようになりました。
地域の人はクラブの会員になり、自らもスポーツを楽しみながら、週末にはトップチームの応援に集う。何面もある芝のピッチでは子どもたちやユース世代の試合が行われ、クラブハウスは、大人から子どもまでが集まる街のハブのような存在になっています。
驚くべきは、こうした取り組みがブンデスリーガなどのトップリーグだけでなく、4部や5部リーグ所属の小さなクラブでも実現していること。まさに「まちの中心にクラブがある暮らし」が地域に根づいているんです。
一方の日本を見ると、都市計画としてスポーツ施設を位置づけてこなかった歴史があります。空いている土地に体育館を作りました、運動公園を作りました、という例が多い。仮に街の中心部の公園内に運動場があったとしても、それを地域のクラブがコミュニティの拠点として有効活用するような、いわゆるソフト面の連携もうまくできていません。
こうしたヨーロッパサッカーと日本サッカーの比較について、先端科学技術研究センターのメンバーである木村正明特任教授らとともに、「ヨーロッパのクラブに比べてJリーグのクラブの企業価値は過小評価されている」という内容の研究論文を2024年に発表しました。メディアでも紹介され、同テーマのフォーラムも大きな反響を呼びました。


── では、この研究を重ねた先にはどんな展望があるのか? 現代のさまざまな課題に対して「まちづくり」「スポーツまちづくり」が果たせる意義を、小泉教授は次のように語る。
「まちづくり」とは単に建物や施設といったハードだけでなく、コミュニティというソフトをどう育てるかが問われるものです。少子高齢化が進むような社会、あるいは都市化が高度に進むような社会というのは、地域コミュニティがどんどん脆弱になっていく一方で、子育て支援や高齢者のケアなど、本来コミュニティで支え合うべきサービスの必要性は高まっていきます。
そうした課題に対して、新たな処方箋となりうるのが「スポーツまちづくり」です。スポーツを通じて人と人の社会的な関係ができることで、結果的に高齢者のケアや子育て支援といった課題の解決にもつながっていくのではないか、ということに期待しています。
── さらに、「スポーツまちづくり」は健康増進やWell-beingとも親和性が高い。
高齢者の健康維持において、最も効果的なのは「社会参加」だと言われています。つまり、単純にスポーツをするだけでなく、その場で仲間が出来たり、地域に居場所ができたりすることが、実はとても大きな意味をもつ。だからこそ、いわゆる「スポーツまちづくり」のようなアプローチで、人とのつながりを生むコミュニティを作っていくことが求められるはず。
そういった社会参加の観点でも、「スポーツまちづくり」という考えはこれからの日本において、地域づくりの重要なエレメントの一つとして、普通に取り組まれるものになると確信しています。

── これからの社会問題とも密接に絡む「まちづくり」と「スポーツまちづくり」。だからこそ、多くの企業とも共創できる要素は大きい。小泉教授が取り組む「ミライ構想カレッジin小布施」もそのひとつだ。
9年ほど前に「東大先端研・小布施町コミュニティ・ラボ」を立ち上げ、住民参加型の「自律共創のまちづくり」として、人口1万人のまち・長野県小布施町の集落の再生などに取り組んでいます。2024年からはNTT東日本にも参画していただき、「ミライ構想カレッジin小布施」という新たなプロジェクトを開始。「人口1万人の町から、2050年のミライを描く」と掲げた取り組みを始めています。
小布施町では全国に先駆けて「若者会議」を実施するなど、積極的に地域づくりに関わる人(=関係人口)を増やそうという取り組みを続けていますが、小さな自治体ですので、その地域の人的資源には限界があります。そこで、NTT東日本の通信力、先端的なICT・デジタル技術を組み合わせることで、地域に暮らさなくても通いや遠隔から地域づくりに関わってくれる人を増やし、より地域の自立性を高めていこう、というのが狙いです。
実際に「小布施町で働きたい」と外から人が入ってくる流れができていて、「技術分散型コミュニティ」のモデルになるんじゃないか、と期待しています。

── 人と人、大学と自治体、さらには企業との掛け算や化学反応こそ、今後UTSSIとしてもっと積極的に取り組んでいくべきこと、と小泉教授は語る。
まちづくりにおいて重要なポイントは、住民参加で作ること、もしくは住民が主導して作ること。ただ、社会課題が複雑化していて、住民だけでは解決できない問題も増えています。だからこそ、企業の力を上手く組み合わせてソリューションを生みだし、住民が納得するような形でのまちづくりが求められています。
「スポーツまちづくり」も同様です。スポーツと先端的な研究を掛け合わせたプロジェクトは、多様な可能性を秘めており、私も多くのことを学んでいます。地域や企業との双発的なプロジェクトがこれからも生まれ、日本のスポーツ研究をリードする組織であり続けたいと考えています。
UTSSIの魅力は、私のようにスポーツを専門としていない研究者も自分の専門性を活かしてスポーツの領域に関われること。まさに東京大学の総合知が集まる場所であり、それがUTSSIの面白さでもあります。今後は、これまで以上にUTSSIメンバー同士の相互交流を増やしていくことで、もっと多様で新しい取り組みが次々と生まれてくるといいな、と思います。
プロフィール

小泉秀樹(こいずみ・ひでき)東京大学大学院工学系研究科 教授。専門はコミュニティ・デザイン、協働によるまちづくり、市民主体の地域再生。1993年、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了。東京理科大学理工学部建築学科助手、東京大学工学部都市工学科講師・助教授・准教授などを経て、現職。共著に『コミュニティデザイン学――その仕組みづくりから考える』(東京大学出版会)、『東日本大震災 復興まちづくり最前線』(学芸出版社)、『まちづくり百科事典』(丸善)、『持続可能性を求めて』(日本経済評論社)など。
取材・文/オグマナオト
撮影/石垣 星児
関連リンク UTSSIについて(企業・各種団体のみなさまへ)